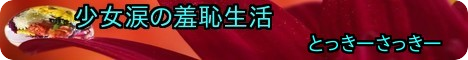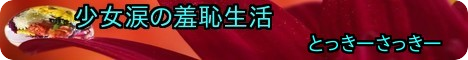 (十五)
(十五)
八月 十一日 月曜日 午後十時三十分 早野 有里 取り敢えず、危機は回避されたみたい。
でも、あの人大丈夫かしら?
あまりにもの咄嗟の出来事で、わたしにも何が起きたか良く分からない
の。
「……よくも、この私に……」
ぼそっとつぶやくような声が聞こえて、そーっと振り向くと、憎悪の炎
に染まった両目が……!
やっぱり、大丈夫じゃないみたい。
今さら、ごめんなさいって謝っても、許してくれそうもないよね。
もしかしたら、わたし……殺されるくらい犯されるかも……?!
……でも、動けないよ。
……体力も限界。
恥ずかしいくらいあそこが丸出しで、それなのに、太ももを閉じ合わせ
る力も残っていない。
「ご気分はッ……いかがですかッ!?」
ほら、来たっ!
気のせいだと思うけど、語尾が苛立っている。
わたしは、残りの体力を振り絞って、何とか股だけでも閉じ合わせた。
でも……もう無理。
後は、ひたすら謝ってなんとか誤魔化そう。
…… ……
……? ……?
……ん?
まだ、何もしてこない……?
わたしは、もう一度、そーっと振り返った。
……? ……?
うーん?……?
……大丈夫……かな。
あの人の自慢の息子。シュンとうつむいて小さくなっている。
「安心なさい。今日はこれ以上、何もしません。
それより、あなたの拘束を解かないといけませんねぇ」
副島は、わたしの視線に気が付いたのか、自信喪失気味の息子を片手で
隠してみせた。
百パーセント信じたわけじゃないけど、選択肢も残っていない。
「少し、触りますよぉ。いえいえ、その気はありませんから」
男の両腕が、肩と腰の下に差し込まれる。
思い出したくない嫌な感覚が肌を刺激して、思わず小さく叫んだ。
「だからぁッ、なにもしません。信じて下さいよぉ」
わたしの身体は、ソファーの上でひっくり返され、顔が、座席部分に押
し付けられた。
きっと、美しい背中のラインと、剥き身のようなお尻に、男の両目が釘
付けになっているのに違いない。
やっぱり、襲われるかも……?
……まさか、お尻じゃないよね?
脳裏にいけない想像が流れ込んできて……これって、過剰な自己防衛?
でも、身体は勝手に、尻たぶの筋肉をキュッとすぼませて、太ももの隙
間を埋めてしまう。
「我ながら、ほれぼれする縛りですねぇ。ほら、ここを引っ張ると……
見事なものでしょう」
シュッ、シュー……シュー、シュッ……
生地の擦れる音と手首に訪れる解放感……
両腕に、久々の自由が戻って来た。
……?
……と、いうことは?
「終わりましたよ、有里様」
……何も起きないの?
……わたしのお尻に触らないの……?
…… ……
良かったという気持ちと、なんでよって思う、いけない心……
でも、身体は勝手に緊張を解き、お尻の筋肉を緩ませた。
…… ……
…… ……
……パッシーンッ!!
「ヒィーッ! イヤーッ!」
肌を打つ乾いた音と、乙女の悲鳴!
お尻に拡がる惨めな痛み。
卑怯よ、今頃叩くなんて……それも、思いっきりッ!
「あっ、これは失礼。つい、うっかり……ははははッ」
わたしは、うつ伏せのまま、キッと睨みつけて……すーっと目をそらし
た。
背筋に冷たいものが走る。
顔は、笑っているのに……目は笑っていない?
冷たい……そう、初めて会ったときのあの目……
これ以上、目を合わせるべきではない。
わたしは、慌てて顔を伏せて、縄に傷めつけられた手首を愛おしそうに
撫でさすった。
そこには、深く刻み込まれた何重にも渡る縄目の跡……
剥がれた皮膚の下から、血がじっとりと滲み出している。
「ごめんね……」
じっと見ていると無性に悔しくなって、まぶたから、また水滴が流れ落
ちた。
「あなたの手首の痛々しさ……そそりますねぇ。
2、3日で傷跡が消えてしまうのが、実に惜しい。
どうせなら、生傷の絶えない肌をさらすのも、これまた一興ですがね……
ククククッ……」
いかにも、この人らしいサディスティックな言葉……
わたしは心をなだめて、傷ついた手首を男の性的な視線から逃すように、
ふくらみの下に仕舞い込んだ。
「ところで、いつまでそんな姿を晒しているのですかぁ……?
いい加減服を着ないと、風邪を引きますよぉ」
副島は、脱ぎ捨てた下着を身に着けながら、うつ伏せのまま動こうとし
ないわたしを、興味深そうに見下ろしている。
「ほっといよ。行為が終わったのなら、わたしには構わないで……!
もう少し……こうしていたいのッ!」
「ふふふっ……変わったお嬢さんですねぇ。ただ、身体には注意して下
さいよぉ。何といっても、あなたの行為次第で、お父さんの寿命が変動
しかねませんから……」
なにを言われようと、今はこうしていたいの……
鉛のように重たい手足も休ませてあげたいし、その間に、火照った肌を
エアコンの風が、心地よく冷ましてくれそうな気がするから……
でも、これは言い訳かも……
本当は、男に見られながら下着を身に着けるのが恥ずかしいから。
行為の後、ベッドからそっと抜け出して、服を身に着ける彼女……
それを知っていながら、背を向けて寝た振りをする彼氏……
女の子なら、こういう男性に魅かれると思うけどね。
……この人には、絶対無理だろうな。
それとね。さっき、気が付いたんだけど……わたし、お洩らししたのか
な?
腰の下に小さな水溜りがあって、それが太ももにひっついて気持ち悪い。
……別に、匂わないけどね。
「有里様、そのまま寝ていても構いませんが、今晩はどうされますぅ?」
またなにか言ってる……
そんなに裸で寝ているのが、気になるのかしら……?
……?……今晩……?
……だめ、頭がもやもやしてて、今は何も考えられない。
「なんなら、タクシーを呼びましょうか? 今からだと、11時過ぎに
は帰れると思いますが……」
「…… ……」
「どうされますぅッ!」
副島が苛立っている。
……今晩って言ったよね……
……お母さんには……会えないよね……
こんな顔見せたら……笑顔を作っても、悲しませることになるかも……
「……あのぅ、このまま、泊まってもいいですか……?」
「それは、構いませんが……」
副島は、わたしの心を掴みかねているみたい。
……やっぱりこの人、女心が分かっていない。
「まあ、いいでしょう。分かりました。そのように手配致しましょう」
「ありがとう……ございます」
なぜか、お礼の言葉が素直に出なかった。
「後のことは、あなたを案内した男にでも聞いて下さい。
連絡しておきますので、しばらく待ってもらえれば来ると思いますから……
……ではお先に、有里様……」
時間を気にしているのか、それとも機嫌が悪いのか……
やや早口に要件だけ伝えると、副島は後ろ手を振りながら、わたしを置
き去りにして部屋を後にした。
「あーあ、行っちゃった……」
扉が閉まり、静けさを取り戻した応接室に、わたしだけが取り残される。
散々傷めつけられたのに、心には薄もやのような安堵感だけが広がって
いる。
屈辱・恥辱・恐怖、もっと、いろんな感情が湧き起ると思ったのに、も
っと、もっと辛いはずなのに……涙が出てこない。
……どうして? ……どうして……?!
……もう、涸れてしまったの……?
テレビドラマだったら、こんなシーンで悲劇のヒロインは号泣するのに、
涙がないと出来ないじゃない。
「ふふふっ……ははははっ……」
なーんか、おかしい。
急にバカバカしくなってきて、そうしたら……睡魔の顔がこっちを見て
いる。
やっと終わったんだし、ちょっとだけ休もう。
わたしは、気だるく少し心地よい気分で、両目を閉じた。