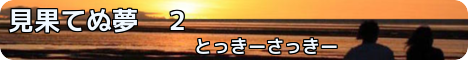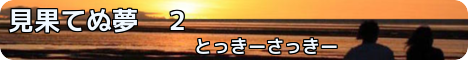 (24)
(24) 『キツネうどん』なんて、裏メニューにもないかも。
でも、これ以上信人を巻き込むわけにはいかない。
もし河添と全面対決になっちゃったら、あの人の一生が終わっちゃうも
の。
あの人が立ち上げた会社だって。
でも不思議。美里はあの人を利用しようとして接近したのにね。
きっと酔いどれ天使さんが、矢を間違えて美里と信人に射ち込んじゃっ
た。
たぶん、そうに違いない。
わたしは長い廊下を、足音を忍ばせて進んだ。
そして信人が教えてくれた、『花山』の別館へと向かう。
別館といっても、わたし達がいた本館とは渡り廊下みたいなので繋がっ
ているから、移動は簡単なんだけど、でもここからは慎重にしないと。
たぶん、いかがわしいというかエッチなことをするために、この別館を
建てたようなものだからって。
これも信人の入れ知恵だけど。
でも、この建物って思ったより小さいわね。平屋建てだし。
……ん? 突きあたりの部屋から笑い声? それもひとりではなさそう。
4人? 5人? ううん、もっとかも?
自然に、足の裏を踵から下ろしていた。
ゆっくりと忍者さんになったつもりで、壁に背中をひっつけながら進ん
でいく。
「は、はあぁぁ……そ、それは……違います。んふぁぁっっ、お豆がぁ
……感じちゃうぅぅっっ!」
「な、なに?! 今の声……?」
ざわついた男たちの歓声に紛れて、今度は女の人の声が聞こえた。
同時に美里の足が急停止する。
鼻から抜けるような甘ったるい声。それなのに、とっても懐かしい響き。
もしかして、典子お姉ちゃんなの?!
足を拡げれば3歩で到着するのに、わたしは赤ちゃんのように這い這い
の姿勢を取っていた。
四つん這いになって、白く輝く障子を目指した。
「おおっ、すまんな。糸を引いていたから、つい納豆かと……それにし
ても、いい眺めだ」
「はぁっ……んっ……んっ……そ、そこを、それ以上……あっ、ああぁぁ
ぁっ」
だみ声の男が声を裏返して、典子お姉ちゃんがまた甘い声で鳴かされた。
逸る心と膨らみ続ける恐怖に、込み上げる唾を何度も飲み干して、わた
しはそっと腕を伸ばした。
部屋を支える柱と障子の間に僅かな隙間を作ると、右目を当てた。
限られた視野をいっぱいに使って、部屋の中を覗き見する。
案の定、下品な顔をした男たちが見える。
大きな座卓を囲むように、箸を手にした男たちが全部で8人。
だけど、肝心の典子お姉ちゃんはどこなの? そうだ、河添は?
わたしは、もっと中を覗こうと障子の隙間を拡げた。
拡大した視野の隅々にまで黒目を走らせてみる。
その時だった。
わたしの真ん前で背中を向けていた男が立ち上がったのは……!
「う、うそ?! なんなのよ! いったい何を?!」
酸素の切れかかった金魚のように、口をぱくぱくさせていた。
目に飛び込んだものがなんなのか理解できなくて、茫然としていた。
黒光りする座卓と対比するように輝く白い肌。
女の人だよね? 引きつらせた呼吸をするたびに、お椀を伏せたような
乳房が上下している。
でも、なんなの? そのおっぱいに乗せられているものって?
それって、お料理? お刺身なの?!
「ひゃぁっ! お箸が乳首にぃっ……あ、はあぁぁぁっっ!」
「はははっ、すまんな。刺身を取るつもりが、つい典子ちゃんのサクラ
ンボを。手元が狂ったようだな」
目の前の現実を美里は受け入れられないのに、これがリアルな世界だっ
て。
男の人の箸が伸ばされて、お刺身を取る振りをして尖った乳首を掴んで、
その人が甘くて哀しい声を上げて、おっぱいのお肉がプルンと揺れて。
「ひどい、こんなことって! よくも典子お姉ちゃんを……! 絶対に
許さないから!」
こんな怒り、生まれて初めてだった。
こんな男たち、本当に死んでしまえばいいのに。怖ろしいことを本気で
思っていた。
「おっと、ビールが切れちまった」
酔っ払い男がもうひとり立ち上がった。
そのせいで、仰向けにされた典子お姉ちゃんの身体が下半身まで露わに
される。
きゅっと引き締まった典子お姉ちゃんの下腹部。
やっぱりその部分にも、お料理の欠片が埋め尽くすように並べられてい
る。
そしてここが特等席というように、髪の毛の薄い男が典子お姉ちゃんの
大切な処を覗き込んでいる。
両肘を張って他の男を寄せ付けないようにしながら、その男はマグロの
刺身を箸で掴んだ。
「どれ、醤油の代わりになるか、試させてもらうぞ」
「あううぅぅっ、んんっ! ど、どうぞ……典子の愛液を……醤油代わ
りに……んんーっっ!」
口を開いている間も、典子お姉ちゃんの身体中をたくさんの箸先が刺激
し続けている。
ツマ先をピンとさせて、座卓の上で背中を湾曲させて、その様子を眺め
て低く笑った男は、真っ赤な身を太腿の付け根へと沈めた。
手首を返すようにして典子お姉ちゃんのアソコに、何度も何度もマグロ
の刺身を擦りつけている。
もう、ダメ! もう、我慢の限界!
「アンタ達っ! 許さないからっ!」
障子をバシッと音を立てて開いたわたしは、部屋の中に飛び込んでいた。