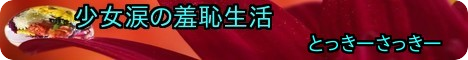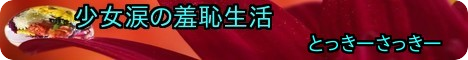 (十九)
(十九)
八月 十二日 火曜日 午前八時四十分 早野 有里わたしが、駅に着いたのは、通勤時間のピークをやや過ぎた頃だった。
駅の構内は、急ぎ足で頑張るサラリーマンさんに混じって、若さと体力を持て余した……要するに、わたしのような学生を、ちらほらと見かけるようになる。
ちょうど、上りの電車が出発した直後なのか、改札口は、降りて来る乗客で込み合っていた
わたしも、その間を縫うようして、いつものようにショルダーバッグから定期券を取り出し……?!
?!……ピタッと歩みが止まった。
後ろに続く若い男性が、不満そうに溜息を吐きながら、わたしの横をすり抜けて行く。
「どうして、あなたが……!?」
顔が一瞬で強張った。
ひとりの男が券売機の端から、手招きしている。
その空間は、エアーポケットのように人気がなくて、まるで人払いの結界でも張っているよう……
でも、ちょっと考えれば、理由は簡単に説明がつく。
この時間帯、乗客のほとんどは定期券を使用し、切符を購入する人なんて極少数だから……
その証拠に、わたしも定期券を持っている。
でも、それどころじゃないくらい、精神は追い詰められていた。
わたしは、誘われるままに、男の……ううん、副島の元へ歩いていた。
「有里様。おはようございます」
副島は、右手を胸に当てがい、頭を大きく下げて、テレビに出てくる執事のような態度で挨拶した。
わたしは一瞬、あっけに取られながら、早口でまくし立てた。
「やめて下さいッ! ……人が見ています。
それに、どうして、あなたがここに来るんですかッ……?」
わたしの地声が大きいのか、副島の態度に興味を惹かれるのか……
何人かのサラリーマンさんが、チラチラと、こちらを窺っている。
「そんな、朝から早口でしゃべらないで下さい。
……頭がキンキンしますよ。
……私は、朝が苦手なんですぅ」
「それなら、来なければいいでしょッ!」
「そうは参りません。私は、有里様の処女をいただいた者として、その後の体調を管理する義務があります。
……因みに、おま○この痛みは、取れましたかぁ?」
……今、何て言ったの……?!
みんながいる前で、また、禁断の単語を……!!
わたし、もう、この駅を利用できないかもしれない。
……ほら、見てよ。
この人のハスキー声に、また何人かがこっちを見ているじゃない。
「ちょっとぉッ、声が大きい。こんな人前で……よくも、そんな……
第一、そんな卑猥な質問……答えたくありませんッ!」
わたしは、改札口に背を向けて、顔を見られないように注意しながら、副島を睨みつけた。
「それは困りますねぇ。あなたは、私に従う義務があります。
……これを、お忘れですかぁ」
そう言うと、ズボンのポケットから折り畳んだ書類を取り出して、表彰式で賞状を渡すように、厳かに読み上げ始めた。
「えーっ、ひとーつ。私の時間、行動は、全て定められた管理者の管轄の下に……」
「……ちょっと、何の真似よッ!」
これって……わたしの契約書……!
……この人、こんなものを持ち出して……許せないッ!
それに、こんな姿を誰かに見られでもしたら……!?
「お願い。こんな所で読まないでよ……
…… ……
わかりました。答えるから……
あの……あそこは……まだ少し痛いです……」
目の周りが熱くなって、声を出そうにも喉が震えた。
そして、答えさせられながら、わたしの視線は周囲を走り回っている。
わたし、またこの男に苛められている。
公衆の中で、こんな恥ずかしい質問に答えさせられている。
「声が小さいですよぉ。それに、面白みのない答えですねぇ。
……まあ、いいでしょう。
それと、出血はしていませんか?
トイレで、ティッシュに血がつくとか……?」
「いえ、大丈夫です。出血もしていません。
……もういいでしょう……講義に遅れたくないのよ」
もう、こんなの嫌ッ!
なんでもいいから早く理由を作って、この場を離れないと……
わたしは、わざと構内の時計に目をやり、乗客の列に戻ろうとした。
「待って下さいよぉ。
……今日は私も付いて行きます。
管理者は、契約者の生活全てを知る権利がありますからねぇ」
今、なんて言ったの?
この男と大学……?
……冗談じゃないわよッ!
あー、想像しただけで、鳥肌が立ってくる。
わたしは、セールスを撃退するような目で、副島を睨みつけた。
「嫌よッ! そんなのお断りッ!
第一、ここであなたに協力しても、わたしと父には、なんのメリットもないじゃない。
あなたとの行為は、病院のあの部屋だけで充分でしょ。
……それに、ここでは、あなたのだーい好きな撮影も、出来ませんよぉーだ……ふふっ……」
そう。嫌なことは、はっきりと……
そして、控えめ気味の嫌みを……
さあ今のうちに、早く逃げ出す口実を探さないと……
わたしは、この状況から脱出しようと、援軍を求めるように周囲をぐるりと見回した。
誰か知り合いでも……
でも、この男と一緒というのは困るし……
何か、良い材料はない……?
きみも、暇そうだから探してよ!
「いいえ、そうとも限りませんよぉ。
まあ、それは追々説明するとして……ちょっと切符を買うので、待っていてもらえませんか?
えーっと、小銭入れは……」
なによ、副島の自信過剰な態度は……
わたしは焦っているのに……ダメッ、イライラしてきた。
……ん? きみ、何を見ているの?
あっ、副島が財布から小銭を取り出そうと、中を覗き込んでる。
……そういうことね。
では、今のうちに……
わたしは、そーっと、男の背後に回ると、定期券を取り出した。
そして、一気にダッシュッ……!
目指すは、乗降客で込み合う改札口……
電光掲示板の文字が、目に飛び込んで来る。
残り1分で下り電車が発車……ッ!
「有里さぁーん。待って下さぁーい」
券売機の方から変な声が聞こえるけど、あれは、わたしには関係ありません。という顔? をして、2階の乗降ホーム目掛けて全力疾走した。
目の前に、エスカレーターと階段が立ち塞がる。
……さあ、どっち?
わたしは、迷わず階段を選択すると、一段飛ばしで一気に駆け上がる。
猛然としたダッシュに、何人かの乗客が、驚いて振り向き立ち止まった。
でも、今はそれどころじゃないの、ごめんね。
胸の中で手を合わせながら、ラストスパートをかける。
これってまるで、高校時代にやらされた階段ダッシュみたい。
まさかこんな時に、部活で先輩にしごかれた経験が、役に立つなんて……
ホームに駆け上がったわたしの前方に、銀色の車両が姿を現した。
……息が上がってくる。
鈍い痛みが、再び股のつけ根を襲ってくる。
でも、あの男と一緒の一日を想像すると、こんなの全然我慢できる。
もう少し……なんとか間に合いそう。
わたしは、空いている扉からすれすれで駆け込んだ。
同時に発車ブザーが鳴り、背後の扉が、エアー音を二度残しながら閉まっていった。
「はあっ、はあ……はあっ、はぁ……」
こんなにハードに身体を動かしたのは、何カ月ぶりだろう。
まだ、心臓がドクンドクンと鳴っている。
こんなことなら、毎朝、ジョギングか何かしておけば良かったかな。
「すーっ、はぁー。すーっ、はぁー……」
わたしは呼吸を整えようと、大きく息を吸い込み、ゆっくり吐き出し、それを何度か繰り返した。
窓の外の景色がゆっくりと流れ出し、車両は軽いモーター音を響かせながら、何事もなかったように走り始めた。
……まさか、乗ってないよね。
わたしはさりげなく周囲を見回して、安心したように、ふーっと息を吐き出した。
気が抜けたせいか、髪の生え際から玉粒みたいな汗が、後から後から流れ出し、ほっぺたから首筋をベットリ濡らしている。
「どうして朝から、こんな目に会わなきゃならないのよッ……!」
わたしは腹立たしげにつぶやきながら、いつもの定位置に身を寄せると、ショルダーバッグからハンカチを取り出し、押えるようにして丁寧に汗を拭い始めた。
もう、こんなのこりごり……
きみも、疲れたでしょ?
わたしの後ろをピタッと付いて来てたもんね。
なかなか、やるじゃない。
……ああ、そうだ。さっきはありがとうね。
おかげで、あの男を振り切ることが出来たしね。
これからも、よろしく頼むよ。
目次へ 第20話へ