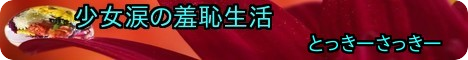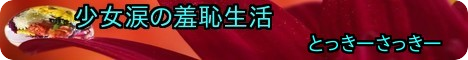 (二十四)
(二十四)
八月 十四日 木曜日 午後五時 早野 有里わたしにとっての悪夢の日から二日が経っていた。
「有里ーっ。あなた宛てに、荷物が届いているわよーっ」
その日の夕方……
ベッドで休んでいるわたしを、お母さんが呼んだ。
もう少し、こうしていたいんだけど……
あら、きみ。来てたのね。
なによぉ、その目は……
今日はバイトをさぼったのかって……?
…… ……
残念でした。
今日はお店、臨時休業だったんですぅーっ。
それで、今まで昼寝をしていたのかって……?
…… ……
それは……当たり……
……だって、言うでしょ。
寝る子は育つって……
もしかしたら、胸が一回り大きくなっているかも知れないでしょ。
わたしは、恋しいベッドに別れを告げると、わたし宛ての荷物を受け取るために、下に降りて行った。
「何かしら……?」
長さは1メートルくらい。
細長い段ボール箱は、何箇所か結束バンドで固定されている。
宛名は……?
……早野有里。うん、わたし。
送り主は……?
……副島徹也。見るんじゃなかった。
「有里、開けるんだったら手伝うわよ」
お母さんが心配そうに、台所から顔を覗かせている。
「大丈夫よ。結構軽いし……」
「……そう。無理だと思ったら、呼んでね」
「……ありがとう、お母さん」
「よいしょっ、よいしょッ……」
わたしは、両手で細長い箱を抱えながら、一段一段、慎重に階段を登っていく。
あの場合、迂闊に開けるわけには、いかないよね。
中にトンデモナイ物が入っていたら、お母さん、気絶するかも知れないでしょ。
当然、わたしは……どうなるんだろう?
「ふぅーうっ……
お母さんには軽いと言ったけど、案外、重たかったな」
わたしは、段ボール箱を部屋に運び入れると、梱包を解いていった。
「……どういうこと?」
箱の中には、ビデオカメラ……それにカメラを固定する三脚……
あと、DVD1枚と説明書……普通の大学ノート1冊……
その他、訳の分からない機械部品がいくつか……
「……まさかねぇ」
ビデオカメラに、嫌ーな予感がする。
「♪、♪……」やっぱり、嫌ーな予感ッ!
突然、携帯から着メロが流れ出した。
「はい。もしもし……」
「こんばんわ有里様。ご気分はいかがですかぁ?」
思わず、携帯を閉じようとした。
あまりにも、タイミングが良すぎでしょ。
まさか? この部屋を盗撮しているんじゃないでしょうね。
まあ、問い質すだけ無駄かもしれないけど……
「ええ、もう大丈夫です。
……それより、この前はタクシーで送っていただき、ありがとうございました」
「随分、しおらしいですねぇ。
……どぉしたんですかぁ?」
「どうもしません。素直に、お礼が言いたかっただけです」
「それは、それは……
ところで、あなた宛てに、荷物が届いていませんかぁ?
細長い箱に入っているはずですが……」
「……ええ、今、届きましたよ。
これで、今度は何をしろと……?」
「さすがは、話が早い。
いえねぇ、このカメラの前で、あなたに色々とやってもらいたい行為が有りまして……」
「具体的に何を……」
「申し訳ございません。
詳しくお話したいのですが、携帯の電池が無くなりかけています。
あとのことは、メールで指示しますので……それでは……」
……プチッ!
「もしもし……ッ!」
副島は一方的に話すと、携帯を切ってしまった。
「……もう、何なのよッ!」
心の中を、釈然としない不安が渦巻いている。
せっかくお昼寝して、いい気分だったのに……
また、気力が落ち込んでいくぅぅぅぅッ。
……副島のバカァァッ!
その夜、わたしとお母さんは、いつもより早めの夕食をとっていた。
普段ならバイトをしている時間だけど、今日は特別……
チビおや……ううん、並木のおじさんに、感謝しなくちゃね。
「やっぱりいいわねぇ。有里とこんな時間に食事をするのは……
それでね……ふふふ……今日はちょっと豪勢にしちゃった♪」
普段の夕食にしては、やけに品数が多い。
肉料理、魚料理、おまけに果物のデザートまで……
今日はお正月? ……それとも誰かの誕生日だっけ……?
「……ほんとだ。
ふふふ……こんなにたんさん、わたし食べきれないよ。
それに何だか……
お父さんの好きな物ばかり並んでいるわよ」
わたしは、ちろりとお母さんを見て、くすりと笑った。
「そうよねぇ……
気が付けば、お父さんの好物を選んでいるのよね。
さあ。冷めないうちに、召し上がれ」
「いただきます……」
どんなに豪華な料理が並んでも、ふたりだけの夕食は、どこか穴が空いているような侘しさが漂っている。
わたしは、食卓越しに母の気持ちを探ろうとした。
この前の気まずい一件……
おまけに熱中症? による、わたしの体調不良……
無言で食事をする母の表情に、ついつい悪い方へ勘ぐってしまう。
「有里、あのね……」
「なに?……お母さん」
声が、引きつるように上ずっている。
わたし……緊張しているのかな?
「ううん、何でもないのよ。
……それより、身体の方は、もう大丈夫なの……?
まだまだ暑い日が続いているんだから、気をつけないと……」
「わかってるぅっ。ちょっと気分が悪くなっただけだから……
心配しないで……
……それに……少しお昼寝したら治っちゃった。
これも、若さの特権でしょ。えっへんっ!」
「もう、この子ったら……
お母さん、真面目に心配してるんだから……ふざけないで……
それと……あのねっ……
その……付き合ってる人ととか……?」
母は、わたしから視線をそらして、話しづらそうにお箸を遊ばせている。
わたしは一瞬、そんなお母さんを可愛いと思った。
同時に、母の思い違いをどうやって解きほぐそうかと、頭を悩ませた。
「やだぁ、お母さん……そんな人……いる訳ないでしょ。
この前はぁ、友達の家に泊まるって……
もう、お母さん、忘れちゃったのぉ……?
……安心してよ、女の子どうしで、募る話を一晩中していただけだから……
あっ、言っておきますけど、わたし、同性を愛する趣味は、ありませんからね……ふふふ……」
わたしは、努めて明るく、笑いを誘うようにごまかした。
そして、挫けそうになる辛い哀しみを、胸に押し留めて、懸命に笑顔を作った。
「ごめんね、有里。
お母さん、変なこと聞いて……」
強張っていたお母さんの表情が、幾分和らいでいる。
ううん、謝らないといけないのは、お母さん、わたしの方……
だって、さっきの指摘、半分以上当たっているんだから……
でもね、これで良かったんだと思うよ。
……思うことにしようよ。
そうでないと……わたし……心が……砕かれて……
……やっぱり、考えるの、やーめた。
「ああ、そうそう……
今日ね、お父さんのお見舞いに行ったら……
あの、やる気のなさそうな看護婦さん、いなくなっていたわよ」
豪華な料理も、旺盛なわたしの食欲? の前に、あらかた片付き始めた頃……
お母さんは思い出したように、話し掛けてきた。
「……えっ! そうなの。
あの人……辞めちゃったの……?!」
「辞めたのか、配置転換なのかは、分からないけど……
今日、松山先生に付いていたのは、若い看護婦さんだったわよ」
「それでお母さん……その彼女に何か聞いてみたの……?」
「ええ。その看護婦さん……
今日から、この病院でお世話になるって……
以前は、隣街の産婦人科病院に勤めていたらしいけど……
人には、色々と事情があるからねぇ……」
母は、黒目を左右に動かしてから、顔を突き出してきた。
わたしも、負けずに顔を突き出していた。
「その人、若いって言ったけど……わたしくらい……?」
「うーん。確か……
21って話してたから、有里よりは、ちょっと上……
でも美人だし……スタイルも抜群だし……
あのフロアーでも、直に人気者になるんじゃないかしら?」
「……まあ、あの階は全部個室で……しかも男ばかりだから……
ある意味、みんな暇でしょうね。
それで、その看護婦さん……名前は何て言うの……?」
「えーっと。水上って言ったかな……
どうせ、有里もまた、お父さんのお見舞いに行くでしょう。
その時にでも、会ってみるといいわ。
それにしても……あの人も幸せね。
あんな美人な看護婦さんに、お世話をしてもらえるんだから……」
「もう、お母さんったら……焼いてるの……?」
わたしは、笑った。
お母さんも、笑っていた。
その後の食卓は、普段の母娘を取り戻して、父の改善しない症状といった、深刻な話から、お母さんの仕事の悩み……
果てはふたりの恋愛感情など……
母と娘だけが通じあえる、ちょっと秘密めいた、温かい時が流れていった。
わたしは、本棚の片隅から、父が覗いているような気がした。
その表情は、穏和で笑顔が溢れ……
仲間に入れて欲しいと、自分を指差している顔だった。
写真立ての父は、いつまでも、子供のように笑っていた……
目次へ 第25話へ