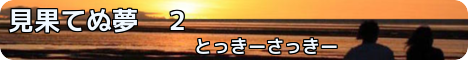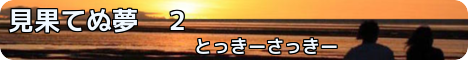 (19)
(19) 俺はベッドに寝転んだまま、飽きもせずに天井を見上げていた。
隣では背中を丸めた美里が、俺の手を握り締めたまま寝息を立てている。
気を張り詰めた反動か、時折大きく息を吸い込んでは、むせるようにそ
の息を吐き出す美里。
こんな年端もいかない少女が背負うには過酷すぎる現実に、俺の胸は痛
んだ。
同時に去来する、彼女の刺激的な告白に始まって、バージンを失った初
夜の光景。
お互いの身体をひたすら求めあった1週間の日々。
「ホントに焼きが回っちまったな。調べるのが生業の探偵が、彼女の胸
の内に気付かずに勝手に上せちまいやがって。ふっ、我ながら情けない
ぜ」
俺は視線を彼女に向けた。
絹のように細くて艶やかな髪に、そっと手を触れた。
俺は……黒川信人は、篠塚美里を愛している。
今なら、誰の目も気にせずに堂々と宣言できる。
年の差なんて関係ない。
彼女が学生だろうと、世間から冷たい視線を浴びせられようと、俺はす
べてを受け止めてやる。
その覚悟を示すように、美里には俺の知りうる情報を全部話して聞かせ
た。
美里の父親でもある篠塚副社長に疎まれ、左遷させられた河添課長の話。
それを恨み、元探偵の俺に娘である美里の身辺の調査を命じたこと。
そして、そのネタを利用して美里を脅迫し、身体を奪い、最終的には、
娘を利用して篠塚副社長を意のままに操る。
その先にあるもの? それは……?!
途方もない計画に、話している俺さえも顔が青ざめていく。
あの天下の時田グループだぞ。
いくら凄腕の社員だとしても、一課長に過ぎない河添が太刀打ちできな
いことくらい、分かっているだろう。
だが、そのショッキングな話のすべてに、美里は耳を傾けてくれた。
俺以上に顔を青ざめさせながらも、顔を逸らすことなく。
「お願い、信人。典子お姉さん……ううん、岡本さんの本当のことを教
えて欲しいの。美里は平気だから」
最後に俺は、河添課長の女にされている岡本典子のことを、知っている
限り教えた。
おそらくは、河添との愛のないセックス。
苦痛と恥辱に満ちた羞恥プレイの数々。
17才の少女にとって酷な気もしたが、俺は真っ直ぐな美里の瞳を信じ
て、プレイの内容を露骨な表現で説明した。
「でも、どうして岡本さんがそこまでして課長に従うのか? 申し訳な
いが、俺にはさっぱり」
「ううん、これで充分よ。ありがとう信人、わたしを信じてくれて。こ
れはお礼ね♪ チュッ♪」
俺の唇を柔らかいモノが触れた。
夢? いつのまにか、俺は眠っているのか?
……いや、それにしては、押し当てられた唇の感覚がやけにリアルだ。
「あら、起きちゃったの? もう少しキスを愉しみたかったのな」
俺の顔をクリクリとした瞳が覗き込んでいた。
そして、リップクリームを塗ったように輝く唇も。
「俺が寝ている間に、盗みキスしたな。ははっ、悪い娘だ」
「ごめんなさ~い。許してね信人♪」
「いや、許さないからな。覚悟するんだ美里」
俺は彼女を下にすると唇を押し付けていた。
唇を開かせて舌と唾液を同時に侵入させた。
「はむぅ、ちゅぶ、ちゅばっ……信人のぉ、おいしい……」
「んぐ、ふんむぅ……美里……」
身体を重ね合わせたまま、俺はガウンの下だけをはだけていく。
昨日からあれだけ愛し合ったのに、自分でも驚くほど勃起したペニスを
美里の女の部分に這わせた。
「ちゅぱぁ、ぷはぁ……硬いのが当たってるよ」
「いいだろ? 入れても」
「うん、いいよ。美里の……お、オマ○コに入れて。信人の……お、オ
チ○チンを……ね」
可愛らしい声だった。恥じらって、聞き取れないくらい細い声だった。
でも小さな星を散りばめた瞳は、俺を見つめてくれている。
俺のペニスを受け入れるように、そっと太腿を開いてくれている。
「美里……愛してる……」
「信人……わたしもだよ……」
俺はゆっくりと腰を下ろしていった。
美里の膣肉を味わうように、ペニスに神経を過敏化させる。
「はあぁ……硬い。信人の硬くて熱いのが……んんっ、美里のお腹に…
…」
愛液で満たされた膣中にペニスが埋没して、美里がしがみ付いてくる。
俺のペニスをもっと深く愛そうとして、両足を腰に絡みつかせてきた。
「いけない子だ。どこで覚えたんだ、こんなポーズ」
「もう、そんなこと、どうでもいいでしょ。それより信人、動いて。激
しく美里を愛して……」
「ああ、好きなだけ愛してあげる。美里のオマ○コを感じさせてあげる」
よっぽど恥ずかしいのか、美里は顔を真っ赤にしたままそっぽを向いた。
そんな彼女に合図の口づけをして、俺は腰を振った。リズムよく滑らか
に。
「んんんっ、はううんんんっ……オチ○チンが、お、お腹の中でぇっ…
…ふあぁんっ」
ペニスを突き入れるたびに美里が甘い声で鳴いた。
その声を、その顔をいつまでも見たくて、俺は腰を振り続けた。
いつのまにか、ホテルの窓ガラスが薄明りに染まっている。
美里と俺の、掛け替えのない記憶が詰まった一夜が終わろうとしていた。